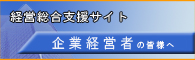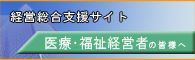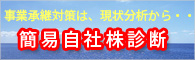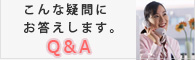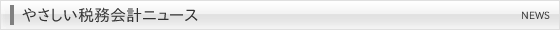
[相談]
 私は昨年(令和6年)、新築住宅を取得し、昨年分の所得税について確定申告により住宅ローン控除の適用を受ける予定です。
私は昨年(令和6年)、新築住宅を取得し、昨年分の所得税について確定申告により住宅ローン控除の適用を受ける予定です。
ところで、聞くところによると、一部の金融機関からの住宅ローンの借り入れについては、住宅ローン控除の適用を受けるための「年末残高証明書」の確定申告書への添付が不要となっているそうですが、その制度の概要を教えてください。
[回答]
ご相談の内容は、住宅ローン控除の適用を受けるための手続について、令和4年度税制改正により、金融機関等が税務署に「年末残高調書」を提出し、税務当局から納税者に住宅ローンの「年末残高情報」を提供する方式(調書方式)に変更する改正が行われたことを指しているものと思われます。詳細は下記解説をご参照ください。
[解説]
令和4年度税制改正において、住宅ローン控除の適用に係る手続について、これまでの年末残高証明書を用いる「証明書方式」から、年末残高調書を用いる「調書方式」とする改正が行われています。
具体的には、所得税法上、令和5年1月1日以後に居住の用に供する家屋について住宅ローン控除の規定の適用を受けようとする個人は、住宅借入金等に係る債権者(銀行など)に、その個人の氏名及び住所、個人番号その他の一定の事項(申請事項)を記載した書類(適用申請書)の提出をしなければならないと定められています。
また、上記の適用申請書の提出を受けた債権者は、原則として、その適用申請書の提出を受けた日の属する年以後10年内の各年の10月31日までに、申請事項及びその適用申請書の提出をした個人のその年の12月31日における住宅借入金等の金額その他の一定の事項を記載した「調書」を作成し、その債権者の本店等の所在地の所轄税務署長に提出しなければならないとも定められています。
ただし、「年末残高調書」を提出する債権者において、上記の改正に対応するためのシステム改修等への対応が困難な場合には、引き続き、従来の「証明書方式」とすることができる経過措置が設けられており、実務上は、この経過措置をすべての金融機関に適用するものと取り扱うこととし、令和6年1月1日以降に居住を開始した人について、対応が完了した金融機関等から、順次、調書方式に移行することとなっています。
国税庁によれば、令和6年12月現在、(公表されているだけで)全国で40程度の金融機関が上記1.の「調書方式」に対応しています。
それらの金融機関からの借入れについて、納税者が住宅ローン控除の適用を受けるためには、金融機関に対し、上記1.の適用申請書を提出することとなります。
また、「調書方式」が適用されている住宅ローン控除について、確定申告や年末調整で適用を受ける際には、税務当局が、住宅ローンの年末残高情報を、マイナポータル等を通じて通知し、その情報を納税者がマイナポータルを通じて取得することで、確定申告・年末調整を行うこととされています。
なお、「調書方式」が適用される場合には、従来の「年末残高証明書」の確定申告書等への添付等は必要ないこととされています。
【留意点】
マイナンバーカードの発行を受けていない等の理由により、マイナポータルを通じて年末残高等の情報を受け取れない人については、金融機関等から交付された返済計画表等の書類により、自身で年末残高を確認し、確定申告書等に入力・記入する必要があることとされています。
[参考]
措法41、41の2の3、令和4年改正措法附則34、措令26の3、措規18の23の2、国税庁ホームページ「住宅ローン控除の適用に係る手続(年末残高調書を用いた方式)について」、同「年末残高調書を用いた方式(調書方式)に対応した金融機関の一覧」、国税庁「住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等情報のマイナポータル連携に関するFAQ(令和7年1月6日)」など
本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。